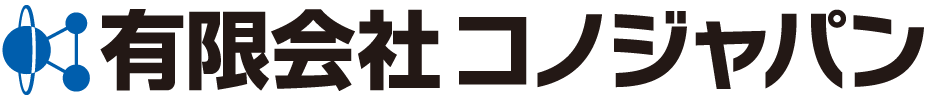むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく、ふかいことをおもしろく、おもしろいことをまじめに、まじめなことをゆかいに、そしてゆかいなことはあくまでゆかいに…これは、小説家であり劇作家でもある故井上ひさし氏の有名なことばです。
私は研修講師として長年にわたり企業研修に登壇してきましたが、今もなお「むずかしいことを、あくまでゆかいに」の域には到達していません。
しかし、「むずかしいことを、わかりやすく」することにかけては、自信があります。
おかげさまで、研修終了後の受講生アンケートや研修ご担当者からは、ほぼ毎回「わかりやすかった」と高評価をいただきます。ですから当社では研修をご依頼いただく際に、研修担当者の方に本気でこうお伝えしています。
「研修のご担当者が研修をオブザーブしていて、今日の研修はわかりにくかったなぁ…とお感じになったら、研修料金はいただきません」
それほど、私たちは「わかりやすさ」にこだわりと自信を持っています。
なぜなら、研修ご担当者や受講生が「わかりにくい」と感じた研修は、研修に集中できないだけでなく、学んだ内容を職場で実践することも難しいからです。
具体的に私たちが実践している「わかりやすい研修」のためのポイントは下記の二点。
1. 受講生を理解する
わかりやすい研修の第一歩は、**相手理解(=顧客理解、受講生理解)**です。
年齢、業務経験年数、職種(技術職か営業職か)、どのような業務を遂行しているか、部下を持っているか、過去の研修受講経験、などの属性を、事前にできる限りヒアリングします。
その情報をもとに、
- カリキュラムの内容や順序を決定する
- テキストの文言をわかりやすく調整する
- 登壇中の説明レベルや専門用語の使い方を変える
- 進行スピードや休憩のタイミングを最適化する
といった工夫を加えます。
同じテーマでも、受講生の背景によって理解しやすい切り口は異なります。
事前準備で相手を理解し、受講生に合わせてカリキュラムを設計することで、研修後のアンケートで「とてもわかりやすかった」と評価される確率は格段に上がります。
2. 丁寧な研修を運営する
もう一つの大切なポイントは、丁寧な研修運営です。
ここで言う「丁寧」とは、受講生一人ひとりを尊重し、その時間と学びを最大限価値あるものにする姿勢と行動のことです。
具体的には、
- 研修開始時に研修の目的や主旨、会社が受講生に期待することを説明する
- テキストの1ページ目から最終ページ目までを説明して全体像とレベル感を伝える
- 受講背同志が互学互習することの重要性を説明し、発言内容は否定しない
- 演習は最初の説明の良し悪しで、演習成果が8割決まってしまう。時間を惜しまずよく説明する
- 演習は気づくことが重要なので、全力を尽くせば結果にこだわらないことを伝える
- 時間配分を守りつつ、受講生の理解状況に合わせて柔軟に進行を調整する
こうした丁寧な対応は、受講生に「この研修は安心できる」「自分を大事にしてくれている」という印象を与えます。その安心感が、積極的な参加や質問を生み、結果として理解度の向上につながります。
私の経験では、同じカリキュラムでも運営の丁寧さによって、受講生の集中度や表情の明るさ、ワークへの参加姿勢は大きく変わります。丁寧に運営された研修は、その場だけでなく、受講後の職場実践にも良い影響を与えます。
まとめ
「相手を理解すること」と「丁寧に研修を運営すること」。
この二つは、研修の「わかりやすさ」を大きく左右する基本です。
受講生の立場に立ち、最適な設計と心のこもった運営を行う――これは、研修講師として大きな使命だと考えて研修運営を行っています。